赤山城址(伊奈氏陣屋跡) 川口市大字赤山766-2

【赤山城址(城趾)】 伊奈氏菩提寺源長寺
赤山城趾の堀を全て掲載へ
伊奈氏は、家康関東入国と共に鴻巣・小室領1万石を給され。熊蔵忠次以後十二代にわたって関東郡代職にあり、関八州の幕領を管轄し、貢税、水利、新田開発等にあたった。三代忠治の時に、赤山領として幕府から7千石を賜り、寛永6年(1629)に小室(現北足立郡伊奈町)から赤山の地に陣屋を移した。これが赤山城で、以来十代163年間伊奈氏が居城したものである。城郭の南方に隣接する源長寺は、伊奈氏の菩提寺として、四代忠克以後の代々の墓があり、五代忠常建立の頒徳碑には忠次、忠政、忠治の業績が刻まれている。
昭和58年3月埼玉県
赤山城趾の堀を全て掲載へ
伊奈氏は、家康関東入国と共に鴻巣・小室領1万石を給され。熊蔵忠次以後十二代にわたって関東郡代職にあり、関八州の幕領を管轄し、貢税、水利、新田開発等にあたった。三代忠治の時に、赤山領として幕府から7千石を賜り、寛永6年(1629)に小室(現北足立郡伊奈町)から赤山の地に陣屋を移した。これが赤山城で、以来十代163年間伊奈氏が居城したものである。城郭の南方に隣接する源長寺は、伊奈氏の菩提寺として、四代忠克以後の代々の墓があり、五代忠常建立の頒徳碑には忠次、忠政、忠治の業績が刻まれている。
昭和58年3月埼玉県

|
 本堂脇の末社(天神社と八幡社)
 鳥居先で参道を道路が横断している
 七代忠順が建立した八幡宮石祠
 赤山山王権現社本殿 |
|
御陣山稲荷 |
||
 |
|
|
  |
||
伊奈半十郎忠治公 |
||
 |
 |
|
|
||
|
||
怒る富士 |
||
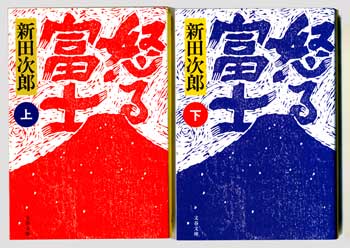 |
怒る富士 上・下 新装版 文春文庫 新田 次郎 上下とも:定価(本体571円+税) 噴火記録, 宝永噴火によって富士山の東山麓は膨大な火山灰に埋まった。噴火後、飢餓に苦しむ山麓の人々を救済するために立ち上がる関東郡代・伊那半左衛門忠順。 内容は以下にあります |
|
二八そば 砂場 川口市安行西立野294-4 電話:048-296-1933 |
|
 |
安行地区を散策するなら、食事処は『二八そば砂場』をお勧めします。 私はもっぱら「もりそば(600円)」オンリーですが、連れ合いは冷やしたぬきそば(夏季限定)、天ぷらそばなどいろいろ注文しています。 なにしろ、そばそのものが旨い、風味、こし、たれ、どれも堪能できる。 写真の車が駐車している側が本通りに面している。駐車場は店の横と、店正面方向の1本先の路地の路地を入ったところにある。 |
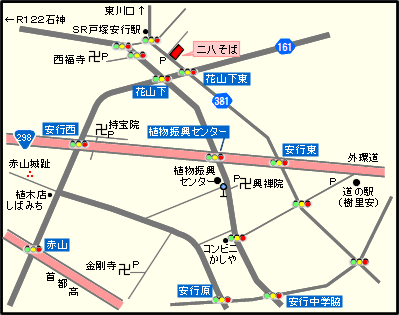 |
 安行の道の駅、樹里安(じゅりあん)の写真。左の高い屋根は安行の植木を販売してる。 |
以下は集めた資料集 |
↑ページトップ | 赤山城趾の堀を全て掲載 |
赤山城址(城趾)と伊奈氏を知ったのは、浮間の歴史を調べていたら江戸幕府編纂の『新編武蔵風土記稿』に関東郡代・伊奈氏の記述があったからで、その後、偶然訪れたところが川口市の赤山城址だった。浮間と多少のつながりもあり写真を数枚載せてHP掲載した。
伊奈氏とはまた偶然が重なり、本屋で新田次郎の小説「怒る富士」(文春文庫)の新装版を手にして読むことになった。

時代は江戸時代中期、年号は元禄・宝永時代、5代徳川綱吉と6代家宣にまたがっている。主人公は関東郡代、伊奈半十郎忠順(ただのり)(7代)である。赤山城址(小説では赤芝山陣屋)と郡代屋敷のあった馬喰町の邸が出てくる。
宝永4年(1707)11月23日午前10時、宝永の大噴火、富士山の中腹が大爆発をして17日間も噴火を続けた。折からの西風で駿東群59カ村に降り注いだ小岩や焼け砂は深いところで一丈四、五尺(約3.3m)にもなった。この地を支配する小田原藩は復旧は無理と「亡所」にし幕府に返地してしまったことも農民の悲惨に拍車をかけた。
このとき幕府が救済に当たらせたのが伊奈氏だった。現地に赴き悲惨さを目の当たりにして、復興と食糧確保に奔走した。降り積もった砂は雨で硬くなり、また捨てる場所にも困った。砂は結局低いところへ流れていくが、酒匂川の大氾濫も起こった。結果的に完全に取り除きに要した年月は36年も掛かった。
幕府財政のひっ迫もあり、幕府の要職はこの災害までも材料にして権力争いにうつつを抜かし、農民の困窮は募るばかり。富士山だけでなく農民も怒った。伊奈は駿府にあった幕府貯蔵米5千俵をかなり強引に放出させ飢饉を救った。
伊奈氏の行動は越権と断定されて郡代職を解任され、小説によると切腹した。駿東群北部の諸村では伊奈半左衛門忠順の徳を慕って処々に小祠建てた。幕府の目を恐れ参拝は一人ずつこっそりしたと言うことである。

時代が移り伊奈半十郎忠尊(ただたか)(12代)の時、天明の大飢饉(天明2〜7、1782〜87、東北地方中心、冷害による)が発生した。この時も伊奈氏は食糧確保に奔走し庶民から高い評価を受けた。だが、関東郡代の職を解かれ改易になり領地は没収、屋敷は取り壊された。両者は共に災害で困窮した人のために奔走したのが共通している、他にも類似するところがあったと思う。幕府の財政の悪化と、忠順時代は柳沢吉保、忠尊時代は田沼意次と言う側用人から将軍の寵愛を受けた専制執政であったことだ。いつの日にか忠尊を取り上げた小説が出ることを願うものです。
その後の伊奈家の消息は不明だが、菩提寺の源長寺墓には新しい卒塔婆が立てられていた。
いつの時代も庶民のために働く御仁は体制からは評価されないようである。遺徳を偲んで、伊奈氏縁の赤山城址と源長寺を紹介するページを大幅に改訂した。現場に数多く掲示してある説明をテキストに取り入れ写真も増やした。
伊奈氏とはまた偶然が重なり、本屋で新田次郎の小説「怒る富士」(文春文庫)の新装版を手にして読むことになった。
時代は江戸時代中期、年号は元禄・宝永時代、5代徳川綱吉と6代家宣にまたがっている。主人公は関東郡代、伊奈半十郎忠順(ただのり)(7代)である。赤山城址(小説では赤芝山陣屋)と郡代屋敷のあった馬喰町の邸が出てくる。
宝永4年(1707)11月23日午前10時、宝永の大噴火、富士山の中腹が大爆発をして17日間も噴火を続けた。折からの西風で駿東群59カ村に降り注いだ小岩や焼け砂は深いところで一丈四、五尺(約3.3m)にもなった。この地を支配する小田原藩は復旧は無理と「亡所」にし幕府に返地してしまったことも農民の悲惨に拍車をかけた。
このとき幕府が救済に当たらせたのが伊奈氏だった。現地に赴き悲惨さを目の当たりにして、復興と食糧確保に奔走した。降り積もった砂は雨で硬くなり、また捨てる場所にも困った。砂は結局低いところへ流れていくが、酒匂川の大氾濫も起こった。結果的に完全に取り除きに要した年月は36年も掛かった。
幕府財政のひっ迫もあり、幕府の要職はこの災害までも材料にして権力争いにうつつを抜かし、農民の困窮は募るばかり。富士山だけでなく農民も怒った。伊奈は駿府にあった幕府貯蔵米5千俵をかなり強引に放出させ飢饉を救った。
伊奈氏の行動は越権と断定されて郡代職を解任され、小説によると切腹した。駿東群北部の諸村では伊奈半左衛門忠順の徳を慕って処々に小祠建てた。幕府の目を恐れ参拝は一人ずつこっそりしたと言うことである。
時代が移り伊奈半十郎忠尊(ただたか)(12代)の時、天明の大飢饉(天明2〜7、1782〜87、東北地方中心、冷害による)が発生した。この時も伊奈氏は食糧確保に奔走し庶民から高い評価を受けた。だが、関東郡代の職を解かれ改易になり領地は没収、屋敷は取り壊された。両者は共に災害で困窮した人のために奔走したのが共通している、他にも類似するところがあったと思う。幕府の財政の悪化と、忠順時代は柳沢吉保、忠尊時代は田沼意次と言う側用人から将軍の寵愛を受けた専制執政であったことだ。いつの日にか忠尊を取り上げた小説が出ることを願うものです。
その後の伊奈家の消息は不明だが、菩提寺の源長寺墓には新しい卒塔婆が立てられていた。
いつの時代も庶民のために働く御仁は体制からは評価されないようである。遺徳を偲んで、伊奈氏縁の赤山城址と源長寺を紹介するページを大幅に改訂した。現場に数多く掲示してある説明をテキストに取り入れ写真も増やした。
写真の石柱には「赤山城址」とありますが、「しばみち」脇に立つ石柱には「赤山城趾入口」と刻まれ、解説板には赤山城跡、赤山陣屋とあるからややこしい。城址・城趾・城跡・陣屋と同じ場所なのにばらばらに使われている。ここでは、「城址」を採用した。
「赤山城趾」の名称で川口市指定文化財に登録されています。
「赤山陣屋」:近くにある赤山歴史自然公園(イイナパーク)の自然歴史資料館・解説板では、「大正11年(1922)に埼玉指定史跡に認定された際、赤山城の名前が用いられたことによります。しかし、その後の調査・研究によって、城でなく、赤山陣屋とするのが正しいことが明らかにされています」。
【関連情報】伊奈町の伊奈氏屋敷跡 |忠次、忠治、忠勝の墓所はこちら

【現地の説明板=川口市教育委員会より】
伊奈氏の系譜
忠次の死後、幕府内での伊奈氏の地位を不動にしたのは、三代忠治である。当初八百石の勘定方として出発した忠治は、寛永19年(1642)には関東郡代に任ぜられ、忠次からの事業を引継おしすすめていった。江戸幕府初期の支配体制・財政基盤確立に果たした忠次・忠治の功績は非常に大きい。
4代忠克以降にも、新田開発・治水事業にとどまらず、災害時の救民活動や江戸深川の市街地化など、伊奈氏の業績は数多い。
しかし、十一代忠敬の後継者として、幕府は板倉周防守勝澄(備前国松山)の十一男忠尊(ただたか)を忠敬の養子として迎え、娘美喜の婿として伊奈家十二代を継がせます。十二代は天明の大飢饉 江戸打ちこわしの収拾などに力を発揮して町人には感謝された。ところが十一代忠敬に実子忠善が誕生。忠敬死去後、伊奈家の主人公として実権を振るいたかった忠尊と忠善。それに伊奈家の権威を阻む幕府。家督相続は「毒殺」や「出奔」に至り、忠尊は営々蟄居。知行没収。忠善は幽閉の身となります。やがて幕府の手によって赤山の陣屋も取り壊され関東郡代伊奈家はここに終止符を打たれます。寛永6年から163年間続いた関東郡代伊奈家。養子の問題はじめとする家内の不始末や、忠尊自身の不行跡を理由に関東郡代を罷免され、伊奈家は改易となった。直参の旗本としては存続し新地1千石で幕末まで続いた。
(※系譜表は末尾にあります)

民政家としての伊奈氏
伊奈氏の業績は、天領の農政担当官としての治水事業だけにとどまらない。災害時の救済活動や、江戸の都市計画などに見せた手腕も特筆すべきだろう。その活躍は、時に江戸町奉行の職域にまで及んでいた。
富士山噴火のあった宝永4年(1707)、七代忠順(ただのぶ)は復旧工事と被災者救済に尽力した(新田次郎の小説「怒る富士」(文春文庫)。また、元禄12年(1699)からの江戸・永代橋架橋工事を行ったのも7代忠順であった。
また、関東郡代伊奈氏の最後の当主となった十二代忠尊も、天明の大飢饉に端を発する天明7年(1787)の江戸打ちこわしの際には、諸国から米を買い集めて江戸市中に大放出するという方法で、見事に難局を乗り切っている。全国的な凶作の中での米買い集めは難しいと見られていたが、伊奈氏を助けようと日々諸国から米が運び込まれたといい、「伊奈半左衛門(忠尊)は世上の沙汰よろしく、町人ども雌伏いたす」という当時の記述とともに、伊奈氏の人気のほどをうかがい知ることが出来る。

関東郡代江戸屋敷図
(安政六年須原屋茂兵衛版の江戸大絵図(江戸古地図))
伊奈氏の江戸屋敷は当初江戸城常磐御門内にあったが、明暦3年(1657)の大火で類焼し、馬喰町に移った。屋敷内には郡代役所があり、伊奈氏改易まで馬喰町郡代屋敷として機能した。 かつての江戸屋敷の位置は、現在の総武線浅草橋の近くにあたる。


「赤山城趾」の名称で川口市指定文化財に登録されています。
「赤山陣屋」:近くにある赤山歴史自然公園(イイナパーク)の自然歴史資料館・解説板では、「大正11年(1922)に埼玉指定史跡に認定された際、赤山城の名前が用いられたことによります。しかし、その後の調査・研究によって、城でなく、赤山陣屋とするのが正しいことが明らかにされています」。
【関連情報】伊奈町の伊奈氏屋敷跡 |忠次、忠治、忠勝の墓所はこちら
【現地の説明板=川口市教育委員会より】
伊奈氏の系譜
忠次の死後、幕府内での伊奈氏の地位を不動にしたのは、三代忠治である。当初八百石の勘定方として出発した忠治は、寛永19年(1642)には関東郡代に任ぜられ、忠次からの事業を引継おしすすめていった。江戸幕府初期の支配体制・財政基盤確立に果たした忠次・忠治の功績は非常に大きい。
4代忠克以降にも、新田開発・治水事業にとどまらず、災害時の救民活動や江戸深川の市街地化など、伊奈氏の業績は数多い。
しかし、十一代忠敬の後継者として、幕府は板倉周防守勝澄(備前国松山)の十一男忠尊(ただたか)を忠敬の養子として迎え、娘美喜の婿として伊奈家十二代を継がせます。十二代は天明の大飢饉 江戸打ちこわしの収拾などに力を発揮して町人には感謝された。ところが十一代忠敬に実子忠善が誕生。忠敬死去後、伊奈家の主人公として実権を振るいたかった忠尊と忠善。それに伊奈家の権威を阻む幕府。家督相続は「毒殺」や「出奔」に至り、忠尊は営々蟄居。知行没収。忠善は幽閉の身となります。やがて幕府の手によって赤山の陣屋も取り壊され関東郡代伊奈家はここに終止符を打たれます。寛永6年から163年間続いた関東郡代伊奈家。養子の問題はじめとする家内の不始末や、忠尊自身の不行跡を理由に関東郡代を罷免され、伊奈家は改易となった。直参の旗本としては存続し新地1千石で幕末まで続いた。
(※系譜表は末尾にあります)
民政家としての伊奈氏
伊奈氏の業績は、天領の農政担当官としての治水事業だけにとどまらない。災害時の救済活動や、江戸の都市計画などに見せた手腕も特筆すべきだろう。その活躍は、時に江戸町奉行の職域にまで及んでいた。
富士山噴火のあった宝永4年(1707)、七代忠順(ただのぶ)は復旧工事と被災者救済に尽力した(新田次郎の小説「怒る富士」(文春文庫)。また、元禄12年(1699)からの江戸・永代橋架橋工事を行ったのも7代忠順であった。
また、関東郡代伊奈氏の最後の当主となった十二代忠尊も、天明の大飢饉に端を発する天明7年(1787)の江戸打ちこわしの際には、諸国から米を買い集めて江戸市中に大放出するという方法で、見事に難局を乗り切っている。全国的な凶作の中での米買い集めは難しいと見られていたが、伊奈氏を助けようと日々諸国から米が運び込まれたといい、「伊奈半左衛門(忠尊)は世上の沙汰よろしく、町人ども雌伏いたす」という当時の記述とともに、伊奈氏の人気のほどをうかがい知ることが出来る。
関東郡代江戸屋敷図
(安政六年須原屋茂兵衛版の江戸大絵図(江戸古地図))
伊奈氏の江戸屋敷は当初江戸城常磐御門内にあったが、明暦3年(1657)の大火で類焼し、馬喰町に移った。屋敷内には郡代役所があり、伊奈氏改易まで馬喰町郡代屋敷として機能した。 かつての江戸屋敷の位置は、現在の総武線浅草橋の近くにあたる。

伊奈家代々の略歴(赤山城以降) |
| 現地に立つ埼玉県教育委員会の解説を採用した |
| 名前・代 | 年 | 業績 | 出来事 |
|---|---|---|---|
| 忠次(初代) (ただつぐ) |
1591(天正9) | 小室(伊奈町)に陣屋を設ける (1550〜1610 61歳) | |
| 1594(文禄3) | 千住大橋の架橋 | ||
| 忠政(2代) | 1604(慶長9) | 備前堀の開削 (1585〜1618 34歳) | 1603 江戸幕府開幕 |
| 忠治(3代) (ただはる) |
1618(元和4) | 赤山源長寺を菩提寺とする忠次の次男(1592〜1653 62歳) | |
| 1621(元和7) | 利根川改修と新川開削 | ||
| 1624(寛永1) | 荒川川瀬の改修 | ||
| 1625(寛永2) | 権現堂川下流に江戸川を開削 | ||
| 1629(寛永6) | 赤山陣屋を設ける | ||
| 見沼溜井の造成・八丁堤の築堤 | |||
| 1638(寛永15) | 勘定奉行となる | ||
| 1642(寛永19) | 関東郡代となる | 1657 明暦の大火 | |
| 忠克(4代) (ただかつ) |
1660(万治3) | 幸手用水の開削 (1617〜1665 49歳) | |
| びわ溜井用水の開削 | |||
| 葛西用水の開削 | |||
| 忠常(5代) (ただつね) |
1666(寛文6) | 両国橋の修築 (1649〜1680 32歳) | |
| 1672(寛文12) | 多摩川通り六号橋の修築 | ||
| 千住大橋の掛け替え | |||
| 1673(寛文13) | 赤山源長寺境内に頌徳碑を建てる | ||
| 忠篤(6代) (ただあつ) |
1692(元禄5) | 飛騨郡代を兼務する (1669〜1697 29歳) | |
| 忠順(7代) (ただのぶ) |
1700(元禄13) | 深川埋め立て普請工事 (?〜1712) | |
| 永代橋の架橋 | |||
| 1704(宝永1) | 本所堤防の修築 | ||
| 1705(宝永2) | 浅草川の修復 | ||
| 1707(宝永4) | 富士山噴火の被害調査、復旧処理 赤山山王社に八幡宮石碑を建てる |
1707/11/23 富士山噴火 | |
| 忠達(8代) (ただみち) |
天一坊事件の解決 (1690〜1756, 67歳) | 1716 享保の改革 | |
| 1719(享保4) | びわ溜井用水の改修, | ||
| 忠辰(9代) (ただとき) |
関東郡代とともに奥右筆組頭の次席に僅か4年で致仕した 忠順の長男、忠逵より受け継ぐ (1705〜1767 63歳) |
||
| 忠宥(10代) (ただおき) |
1764(明和1) | 天狗騒動(秩父地方百姓一揆)を解決 (1729〜1772 42歳) | 1764 伝馬騒動 |
| 1765(明和2) | 勘定奉行となる | ||
| 忠啓(11代) | 1775(安永4) | 勘定吟味役となる 郡山15万石の松平甲斐守吉里の六男 |
|
| 忠尊(12代) (ただたか) |
1784(天明4) | 勘定吟味役となる (?〜1794) | |
| 1787(天明7) | 天明の大飢饉 江戸打ちこわしの収拾 江戸貧民の救済措置 |
1782 天明の大飢饉 | |
| 1792(寛政4) | 関東郡代を罷免される,赤山の陣屋は取り壊され、家臣もあちこちへちらばった | ||
| 忠善(13代) (ただよし) |
1803(享和3) | 大和国郡山城に蟄居。のち享和3年に許されて江戸の松平保光の屋敷に移され、35歳で死去 | 注)13代以下は追加した |
| 忠盈(14代) (ただみつ) |
伊奈家歴代の勲功は大きく、幕府は忠盈(17歳)に伊奈家の名跡を継がせ、武蔵国秩父と常陸国信太郡内の内1,000石を受け小普請に任ぜられ、旗本として幕末にいたった。 | 1867 明治元年 |