千手院 川口市坂下町2-15-5 鳩井山 曹洞宗

【千手院】 広域案内図|日光道中絵図の鳩ヶ谷宿
足立観音霊場の28番札所 →次の札所へ
本尊 千手観世音菩薩

当寺には鳩ヶ谷市指定有形文化財の「銅製鰐口(わにぐち)(写真下端)」が所蔵されている。鰐口は弘治2年(1556)の銘があり。社殿・仏堂正面の軒下につるす、円形で扁平中空の金属製の音響具で、下方が横に長く裂けている。参詣者が布で編んだ縄を振ってならす。
浅間神社は、江戸時代に千手院が管理していた。明治40年に、氷川神社との合祀に際し、浅間神社御神体と共に鰐口は、千手院に移された。
曹洞宗鳩井山千手院は、ふるくは鳩ヶ谷宿のほぼ中央(現本町3-2-20)にあって、観音堂として信仰を集めていた。慶安3年(1650)に、曹洞宗玉龍法性寺末寺となり、そして、昭和45年(1970)に現在の場所に移転した。 鳩ヶ谷市教育委員会掲示物より抜粋
足立観音霊場の28番札所 →次の札所へ
本尊 千手観世音菩薩
当寺には鳩ヶ谷市指定有形文化財の「銅製鰐口(わにぐち)(写真下端)」が所蔵されている。鰐口は弘治2年(1556)の銘があり。社殿・仏堂正面の軒下につるす、円形で扁平中空の金属製の音響具で、下方が横に長く裂けている。参詣者が布で編んだ縄を振ってならす。
浅間神社は、江戸時代に千手院が管理していた。明治40年に、氷川神社との合祀に際し、浅間神社御神体と共に鰐口は、千手院に移された。
曹洞宗鳩井山千手院は、ふるくは鳩ヶ谷宿のほぼ中央(現本町3-2-20)にあって、観音堂として信仰を集めていた。慶安3年(1650)に、曹洞宗玉龍法性寺末寺となり、そして、昭和45年(1970)に現在の場所に移転した。 鳩ヶ谷市教育委員会掲示物より抜粋
 |
 |
|
 |
 |
|
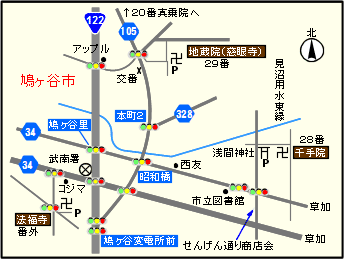
|
上の鳥居の写真は、千手院が別当を勤める浅間神社。 鳩ヶ谷浅間(せんげん)神社は弘治2年(1556)に勧請された古社で、祭神は木花咲耶姫です。江戸時代末まで山の上に建つ唯一の神社で3,200坪の広大な境内を持つ社でした。 明治政府の小社統合令によって、明治40年に鳩ヶ谷氷川神社へ合社になり一時は廃社となりました。けれども、人々の信仰は厚く、昭和53年旧別当寺千手院により再興されて、同院に祀られていた伝来の御本尊が安置されました。 (千手院掲示物より抜粋) 『鳩ヶ谷八景』なるものが存在します。昭和3年(1928)に選定された鳩ヶ谷の風光明媚な場所ですが、ここ、浅間神社も選ばれています。鳥居の左、古木と並んで立つ石碑には「鳩ヶ谷八景、其の一、浅間山の夕照」と刻まれている。選定してからはや80年以上も経ちますから、ここから眺める夕照も今とは違いさぞかし風流な景色だったことでしょう。  鳩ヶ谷市指定有形文化財の「銅製鰐口(わにぐち)」 |
