丂悈恄幮乮偝偄偨傑巗椢嬫戝帤戝娫栘帤敧挌2395斣乯
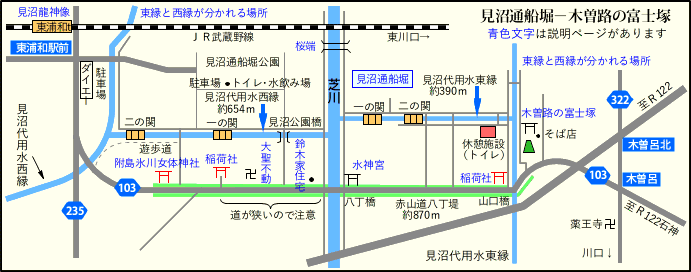


丂悈恄幮偼丄尒徖捠慏杧偑奐捠偟偨梻擭偺嫕曐17擭(1732)6寧偺憂寶偲揱偊傜傟偰偄傞丅嵳恄偼悝徾昉柦乮傒偢偼傔傂傔偺傒偙偲亖悈偺恄丒塉岊偄偺恄乯偱偁傞丅杮揳偼戝惓12擭9寧1擔偺戝抧恔偵傛傝慡夡偟丄摨13擭偵嵞寶偝傟偨傕偺偱偁傞丅
丂 嫕曐16擭丄堜戲栱憏暫塹堊塱偵傛偭偰奐嶍偝傟偨尒徖捠慏杧偑奐捠偟丄峕屗偲尒徖戙梡悈楬墢曈偺懞乆偲偺暔帒桝憲偑壜擻偵側傝傑偟偨丅慏偼戙梡悈楬墢曈偺壨娸偱壸暔乮峕屗帪戙偵偍偄偰偼擭峷暷偑庡偱偁偭偨乯傪愊傫偱峕屗傊峴偒丄婣傝偼旍椏丄墫丄庰側偳偺彜昳傪愊傫偱偒偨丅壸暔偺愊傒偍傠偟傪偡傞壨娸応偼丄幣愳偲搶惣墢梡悈楬増偄偵俆俋偐強丅敧挌偺壨娸応傕偦偺堦偮偱偁傝丄偙偺晅嬤偵偼壨愳桝憲偵偨偢偝傢傞恖偨偪偑廧傫偱偄傑偟偨丅
丂 悈恄幮偼偦偺傛偆側巇帠偵偮偔恖偨偪偑悈擄杊巭傪婩婅偟偰釰偭偨傕偺偱偡丅
丂丂 徍榓58擭3寧丂偝偄偨傑巗乮嫬撪偺宖帵暔傛傝乯
丂 嫕曐16擭丄堜戲栱憏暫塹堊塱偵傛偭偰奐嶍偝傟偨尒徖捠慏杧偑奐捠偟丄峕屗偲尒徖戙梡悈楬墢曈偺懞乆偲偺暔帒桝憲偑壜擻偵側傝傑偟偨丅慏偼戙梡悈楬墢曈偺壨娸偱壸暔乮峕屗帪戙偵偍偄偰偼擭峷暷偑庡偱偁偭偨乯傪愊傫偱峕屗傊峴偒丄婣傝偼旍椏丄墫丄庰側偳偺彜昳傪愊傫偱偒偨丅壸暔偺愊傒偍傠偟傪偡傞壨娸応偼丄幣愳偲搶惣墢梡悈楬増偄偵俆俋偐強丅敧挌偺壨娸応傕偦偺堦偮偱偁傝丄偙偺晅嬤偵偼壨愳桝憲偵偨偢偝傢傞恖偨偪偑廧傫偱偄傑偟偨丅
丂 悈恄幮偼偦偺傛偆側巇帠偵偮偔恖偨偪偑悈擄杊巭傪婩婅偟偰釰偭偨傕偺偱偡丅
丂丂 徍榓58擭3寧丂偝偄偨傑巗乮嫬撪偺宖帵暔傛傝乯

 |
 |
| 悈恄幮傾僢僾 | 幣愳偵壦偐傞恖摴嫶乮嵍乯偲敧挌嫶乮塃乯丄惓柺偼悈恄幮 |
敧挌掔
丂丂丂丂丂丂 偝偄偨傑巗戝帤戝娫栘乣愳岥巗栘慮楥
丂 敧挌掔偼丄娭搶孲戙埳撧敿嵍塹栧拤帯偑抸偄偨恖岥偺掔偱偁傞丅挿偝偑敧挰乮栺870m乯傎偳偁傞偺偱偦偺柤偑晅偗傜傟偨丅
丂 摽愳壠峃偺娭搶擖崙屻丄埳撧巵偼椵戙帯悈帠嬈偵椡傪恠偔偟棙崻愳傗峳愳偺棳楬傪懼偊偨傝燇燆梡悈抮傪嶌傞側偳娭搶抧曽偺帯悈帠嬈傪師乆偵姰惉偝偣偨丅尒徖棴堜傕偦偺堦偮偱偁傞丅
丂 姲塱6擭(1629)丄埳撧拤帯偼椉娸偺戜抧偑傕偭偲傕愙偡傞塝榓巗戝娫栘偺晬搰偲愳岥巗栘慮楥偺娫偵掔傪抸偒燇燆梡悈抮傪嶌偭偨丅偦偺柺愊偼1200噓偵媦傇峀戝側棴堜偱偁偭偨丅偙偺棴堜偼壓棳抧堟221偐懞偺燇燆梡悈偲偟偰巊傢傟偨偑丄戝塉偑懕偔偲斆棓偟偨傝丄姳偽偮偺帪偼悈偑懌傝側偔側偭偨傝偡傞側偳偄傠偄傠晄搒崌偑弌偰丄嫕曐12擭(1727)丄敧戙彨孯媑廆偺柦傪庴偗偨堜戲栱憏暫塹堊塱偵傛偭偰姳戱偝傟傞偵帄偭偨丅
傑偨丄偙偺敧挌掔偼姲塱6擭偵埳撧拤帯偑恮壆傪峔偊偨愒嶳偵捠偢傞乽愒嶳奨摴乿偺堦晹偱傕偁傞丅
丂丂 徍榓58擭3寧丂偝偄偨傑巗嫵堢埾堳夛丂乮敧挌嫶偺榚偵棫偮夝愢斅傛傝乯
丂丂丂丂丂丂 偝偄偨傑巗戝帤戝娫栘乣愳岥巗栘慮楥
丂 敧挌掔偼丄娭搶孲戙埳撧敿嵍塹栧拤帯偑抸偄偨恖岥偺掔偱偁傞丅挿偝偑敧挰乮栺870m乯傎偳偁傞偺偱偦偺柤偑晅偗傜傟偨丅
丂 摽愳壠峃偺娭搶擖崙屻丄埳撧巵偼椵戙帯悈帠嬈偵椡傪恠偔偟棙崻愳傗峳愳偺棳楬傪懼偊偨傝燇燆梡悈抮傪嶌傞側偳娭搶抧曽偺帯悈帠嬈傪師乆偵姰惉偝偣偨丅尒徖棴堜傕偦偺堦偮偱偁傞丅
丂 姲塱6擭(1629)丄埳撧拤帯偼椉娸偺戜抧偑傕偭偲傕愙偡傞塝榓巗戝娫栘偺晬搰偲愳岥巗栘慮楥偺娫偵掔傪抸偒燇燆梡悈抮傪嶌偭偨丅偦偺柺愊偼1200噓偵媦傇峀戝側棴堜偱偁偭偨丅偙偺棴堜偼壓棳抧堟221偐懞偺燇燆梡悈偲偟偰巊傢傟偨偑丄戝塉偑懕偔偲斆棓偟偨傝丄姳偽偮偺帪偼悈偑懌傝側偔側偭偨傝偡傞側偳偄傠偄傠晄搒崌偑弌偰丄嫕曐12擭(1727)丄敧戙彨孯媑廆偺柦傪庴偗偨堜戲栱憏暫塹堊塱偵傛偭偰姳戱偝傟傞偵帄偭偨丅
傑偨丄偙偺敧挌掔偼姲塱6擭偵埳撧拤帯偑恮壆傪峔偊偨愒嶳偵捠偢傞乽愒嶳奨摴乿偺堦晹偱傕偁傞丅
丂丂 徍榓58擭3寧丂偝偄偨傑巗嫵堢埾堳夛丂乮敧挌嫶偺榚偵棫偮夝愢斅傛傝乯